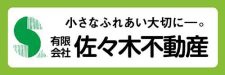安藤建築事務所
電話
076-209-6682
安藤建築事務所
SNSの見過ぎにも注意が必要
2024年12月01日
こんばんは!!
家づくりをする際に、わからないことや気になることを
SNSで調べませんか?
SNSで調べませんか?
最近だと、耐震等級や断熱等級、家づくりの失敗談や
あれを取り入れて正解・不正解というような内容の物も
大量にあふれていると思います。
参考にする分にはとてもありがたいツールですが、
傾倒しすぎると、そうでなければならないというような志向に
意識が集中してしまい、家づくりを楽しく行うことができなくなります。
当たり前のことですが、耐震等級は3がとれて、
断熱等級は7で、なおかつ気密性も保たれる。
その上で自然素材がふんだんに使われていれば最高です。
すべてを叶えようと思うと当然お金がかかります。
その中で考えるのはニッチな家なのか
バランスの取れた家なのか。
ニッチな家とは耐震等級に全振りしたり、断熱気密に全振りしたり、
バランス重視だと
耐震等級2でUA値0.6でC値が0.5~0.7程度、床は無垢フローリング
というような感じでしょうか。
これらに関しては正解がありません。
耐震等級3が必須という方もいれば
断熱等級7が必須という方もいます。
でも、それはあくまで個人の意見で
どんなに有名な方が説明していても、決めるのは自分たちです。
その人のいうことを聞いて
家づくりが失敗に終わってもその人は責任をとってくれません。
むしろ大切なのは、SNSで発信をしている人よりも
実際に建ててくださる建築会社の考えを聞く方がとても大切に思います。
そして、SNSについて学んだことについて
建築会社に相談することも大切だと思います。
建築会社もすべての情報をもっているわけではありません。
でも、その事柄について検討し、どういう回答が得られるかは
とても大切なことだと思います。
ネットで調べて、みつけてきたものを建築会社に使うように指示をして、
万が一失敗に終わったときはそれを使いたいと言った自分たちの
責任となるため、しっかりと話し合うことが大切です。
お客様がC値は0.3以下じゃないとダメだと、気密をやっていない会社にお願いしたとして、
C値自体は0.3を切っても、内部結露対策や断熱に対する考え方が間違っていたら
躯体はすぐにダメになります。
この場合は気密をやっていない会社が悪いのではありません。
だって、超高気密が正解だと世の中で認められていないのです。
その会社は理由はどうあれ、気密工事をしていない会社だったので
そんな会社に気密と壁体内結露に対する知識を詰め込ませる方が
難しいからです。
でも、その会社は気密はやっていなくても、素晴らしい家づくりをして
お客様の満足度は高い可能性があります。
耐震等級も同じです。
例えば大開口や吹き抜けがある空間が得意な建築会社に
耐震等級3をお願いしたときには、やはり閉鎖的になってしまいます。
さらに、死ぬまで大地震がこなかったら耐震等級3も意味がないかもしれません。
正しいか正しくないかを誰かが決めること自体おかしいことなのです。
正しいか正しくないかの解釈は
各家庭によるもので、まわりの人がこれが絶対だなんてのは
思いあがりもいいところです。
家づくりのこだわる点として大きなところが
デザイン
耐震性
断熱気密性
素材
価格 等でしょうか。
これらの中で優先順位を決めて、その考え方が
一番近い会社を選ぶことがなによりも大切で
知識を押し付けることではないのです。
情報が溢れすぎていることで、ちょっと気になりだすと
あれもこれも心配になるなんてことはありませんか?
残念ながら、家づくりですべてを100%手に入れるのは難しいのです。
もちろんそれに向かって建築会社さんと一緒に頑張って建てるのですが、
迷ったときには楽しいか楽しくないかです。
性能が暮らしを楽しくしてくれることはありません。
そして、家づくりをするのは機械ではなく、何十人もの職人さんです。
それぞれ個性がありますし、もちろん出来不出来もあるかもしれません。
それらも含めて家づくりなのです。
お客様の不安や心配を一緒に共有してくれて、
的確に進めてくれる現場監督さんがいて、
それに応えようと職人さんが頑張ってくれる。
それが家づくりだと思います。
でも、SNSで自分の家の粗探しをして
建築会社の名前とその部分の写真をアップするような
記事も少なくありません。
仕上がりが悪いなと思えば担当さんに相談すれば良いですし、
それで対応があんまりだったら上司の方に相談すれば良いと思います。
もちろん、そんな話が一切通用しない担当者や会社もあります。
良くSNSで見るのが、契約金を払ったとたんに連絡がくるのが
とても遅くなったという記事や、
いつまでたっても着工しない等、問題も確かに多いです。
もっともっとお互いを思いやりながら家づくりができればと思います。
話がかなり脱線しましたが、世の中の情報も大切ですが、
建築会社との関係性もとても大切ですので
ぜひ、情報をぶつけるではなくそれに対しての考えを聞いてみる
というような進め方をしてみてはいかがでしょうか。
閲覧履歴