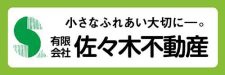安藤建築事務所
電話
076-209-6682
安藤建築事務所
家づくりの断熱のウラ側
2025年10月07日
―「あたたかい家」と「結露しない家」は、同じようで少し違う話―
1. 断熱と気密って、そもそも何のためにあるの?
家の「断熱」と「気密」は、どちらも快適で長持ちする家に欠かせません。
断熱は「熱を伝えにくくして、冬にあたたかく・夏に涼しくする」仕組み。
気密は「スキマ風をなくして、計画通りの空気の流れを保つ」仕組み。
この2つがしっかりしていると、家の中は少ないエネルギーで快適になります。
でも、どちらかが弱いと、「壁の中で起こるトラブル=壁の中の結露」につながることがあります。
2. 壁の中で起こる“見えない結露”とは?
冬、窓ガラスに水滴がつくことがありますよね。
あれと同じことが壁の中で起こるのが「壁体内結露(へきたないけつろ)」です。
たとえば冬の朝――
外は0℃、部屋の中は20℃で加湿器を使って湿度60%。
そんな状態だと、壁の中のどこかで「約10℃くらい」に冷える部分があります。
その温度のところで、空気の中の水分が水滴になってしまうんです。
それが続くと、壁の中が湿気っぽくなって、カビや木の腐れの原因になります。
3. 断熱の種類によって“乾き方”が違う
実は、どの断熱材を使っても「結露のきっかけ」は同じです。
でも、「結露したあと乾きやすいかどうか」が、断熱材の種類で大きく違います。
ウレタン吹付断熱(発泡スプレータイプ)
壁の中に直接吹き付けて、スキマなく埋めるタイプ。
断熱性能はとても高いです。
でも「水を通さない性質」なので、いったん湿気が入ると乾きにくいのが弱点。
つまり、結露が起こると逃げ場がない構造になります。
グラスウール断熱(ふわふわ綿タイプ)
綿のような素材を袋に入れて壁に詰めるタイプ。
湿気は通しやすいので、きちんと防湿シートと通気層を作れば乾きやすいです。
ただし、施工が雑だとスキマができやすく、性能が落ちやすい点に注意。
プレウォール工法(パネル式の壁)
工場で「構造+断熱+気密」を一体化してつくるパネル。
品質は安定しやすい反面、**ウレタンと合板が密着した“乾きにくい構造”**になります。
雨水の侵入や気密のわずかなズレがあると、中で湿気が抜けずカビが発生するリスクも。
4. 結露が起きるとどうなるの?
木が黒く変色する(カビ・菌)
壁の内側の合板が膨らむ
断熱材が湿って性能が落ちる
シロアリの原因になる
こうした症状は、家の中からは見えません。
外壁を壊して初めて気づくケースもあります。
つまり、「結露しない家」は**“あたたかい家”より一歩上の性能**なんです。
5. 結露しない家にするための3つのポイント
① 湿気の逃げ道をつくる
外壁の裏に「通気層」というスキマを作って、湿気が抜けるようにする。
② 室内の湿気をコントロールする
防湿シートや“可変透湿シート”を使って、
冬は湿気を止め、夏は逃がす「呼吸する壁」にする。
③ スキマをなくす
吹付でもグラスウールでも、“気密施工”を正しくやることが一番大事。
サッシまわり、コンセント、天井や床の取り合いに気を配るだけで全然違います。
6. まとめ:「どんな断熱材でも、壁の中の空気をデザインする」
大切なのは「ウレタンかグラスウールか」ではなく、
それぞれの特性を理解して、湿気が入っても乾ける設計にすること。
あなたの家が「断熱材の性能で快適になる」だけでなく、
「結露しないから長持ちする」ことこそ、本当の高性能住宅です。
閲覧履歴